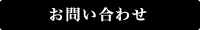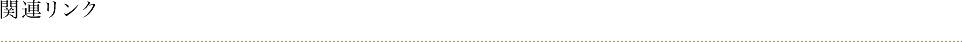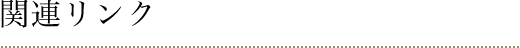北海道の先輩経営者からのメッセージ

毎日同じことの繰り返し、店とモノを大事にする
中堀 彰男 氏
創作和食平成9年10月


ご両親が共働きだったことがきっかけで小さな頃からお料理をしていた。中学生になり、たまたまお母様のパート先に昼ごはんを作って持っていくと、その友人が「美味しい」と喜んでくれて、それが、とても嬉しくて本気で料理の道を志すことに。
高校生になりスポーツを始めると体育の先生への道も考えるようになったが、思案の末、結局、料理の世界へ入ったという。
卒業後、和食の道へ。 1店舗だけでは世間知らずになると思い、数店移り変わる。25歳の頃には、お店を任されるようになるが料理以外の事は分からず、他店を見に行くことや先輩からスタッフの教育やホールのことなどを聞くことで勉強した。
その後、4店舗を構える会社に入ると全店を見て指導する立場となる。ところが腰を痛め、退職。休養している中、中国で中華レストラン&バーを展開するという会社から支社長として行ってほしいとの声が掛かり、中国へ飛ぶ。オープニングの仕事の中には、今まで経験のない面接なども行った。しかしオープンが近づくにつれ、会社の方針とのズレを感じるようになりオープンを見届け、退社することになる。
そして、いよいよ念願だった自店の「創作和食 どりか夢」開業を実現する。オープンで苦労したのは融資。色々な経験はしたものの、自分一人で手続きを行うことが大変だったという。
オープン3年後に現在の場所に移転。個室は畳から洋室へ造り替えたが、他は移転した際に改築した当時のまま。毎日、掃除することで常に清潔に、大事にしているからこそ、改装せずに維持、お客様からもキレイだね、と言われるという。一番大切なのは、お客様。手を抜かない、適当にしない、そしてお客様にゆったりしていただきたいという。
最近は調理も機械化し、技術の伝承がなくなっている。技術はもちろん、レシピなども伝えていきたい、基本を知った上で便利さを使って欲しいと語る。

出来る範囲で、そしてコツコツと
川崎 勇司 氏
ビストロ平成15年3月


学校を卒業して、ホテルニューオータニ札幌の調理へ。その頃から漠然と自分のお店を持ちたい、と思っていたようだ。調理人を目指したのは、手に職をつけたい、料理が好きだから料理人の道へ進んだと語る。その当時は、調理師学校へ進むか直ぐに飲食店で修業するか2タイプが半々くらいだったようで、自分には調理師学校へ進む、という考えはなく、修行の道へ進んだという。
そしてホテルを皮切りに10軒ほどの飲食店で修業、漠然としていた自分の思いが30代半ばくらいから徐々に方向性が見えてきたと話す。
調理人として勤務しながら、場所探しや色々な準備を進め、退職してから2カ月ほどでオープンさせた。初めてお店を持つということは知名度も何もない、やはり路面店が一番良いが、街中でお客様が来られるような場所を探すのは難しく、色々と探していたところ路面店である現在の場所にたどり着いた。
内装は、一から作ったが費用を抑えられるように考えたという。一番大変だったのは、銀行からの融資手続きに関わる交渉関係だったようだ。
お店には約70~80本ほどのスパークリングワインや赤白のワインを常備、そして季節ごとのお料理をお出しできるようにしている。評判が良いのはお肉料理だという。
お客様は飛び込みで来られた方がリピーターに、という方が多く、長年来られている方はもちろんだが久々に顔を見せてくれる方もいるようだ。
オープン当時はホールスタッフもいたようだが現在は一人。
料理もホールも両方やらなければいけないが「大変だ」と言っている状況ではない。出来る範囲でやっていく。そして今来て頂いてるお客様をコツコツと大事にしていきたいと語る。

今この時が人生で最高の瞬間 今日ここでの出遭い 心から感謝
宮岡 秋廣 氏
居酒屋平成24年9月


20歳の頃、喫茶店を経営していたが、結婚して子供が生まれた時、安定を求めてスーパーに勤務。時が経ち45歳の頃、仕事のやりがいなどに疑問を感じ脱サラ。会社を辞めたいと家族に相談した時は、当時1番下の高校二年生のご三男様を始め家族に後押しされたと嬉しそうに語る。現在はご次男様が会社の片腕として無くてはならない存在だそうだ。
そして平成4年、ステーキ弁当専門店を創業。5年ほどは厳しい状態が続いたようだが周りの方々に助けられながら有限会社を立ち上げて、全国の北海道物産展にも出店し、売上は右肩上がりに。ところが2001年に発生したBSE問題で大打撃を受け、会社をたたもうかとさえ考えたが、周りの人やスタッフに支えられ一念発起、売上は徐々に回復していったという。 そして帯広から札幌へ移る。折よくワンランク上の弁当屋を探していた百貨店を紹介され「ステーキ弁当専門店フォーシーズン」を出店。それを機に全国の百貨店にも出店を続けたそうだ。 札幌へ来る百貨店のバイヤーとの食事会も多く、どうせお金を払うなら、その人たちに食べてほしいと思う料理を提供できる自分のお店を出したほうが良いと思ったのが飲食店の出発点だという。 最初は地産地消のものにこだわった「蟹とステーキのお店」、ところが理想と現実は違った。自分が気に入った店では経営が厳しいことに直面する、そしてオープン1年半後、現在の場所へ移転。今は、日替わりメニューや北海道物産展で飛び回りながら仕入れてくる日本酒をお出しする「創作料理と美味しいお酒のお店 北乃家」。15名ほど入れば一杯だがミュージシャンを応援出来る大好きなライヴを不定期に開催している。
移転後、心筋梗塞で倒れる。その時に思ったのが自分は生かしてもらっている、自分の範囲で出来ること、そして頑張っている人たちを応援すること、それが自分の生かされている理由だと吹っ切れた、今までの人との出会い『一期一会』を実感できたからこそ、皆さんに感謝のお礼をしたいという。 これからは縮小していた弁当屋を少し拡大、基盤を固め息子たちへ譲り、「北乃家」は趣味も取り入れたライヴハウスレストランにしていきたい、と夢を語る。

母の言葉“商売は正直に”を実践
吉井 大輔 氏
バー平成25年6月


「お酒、飲めないんです」「すすきのでは“一杯どうぞ“文化があって、それも大切な売上と教わったけど、自分は無理です、ジュースでも良いと言われたけど、その分、お客様が1杯でも多く飲んで頂ければ、それが良いんです」と語る。 一番大切なのは、お客様。誕生日など自分は、そういうところに還元したい、飲食店の人たちが自分の店を閉店後、飲みに来てくれ、こちらも食べに行くこともある、そういう繋がりを大事にしたいと語る。 学校卒業後、建設会社に就職、そんな中“漠然と何かしたい”と思っていたそうだ。 いよいよ自分のお店を持つと決め、人に任せてスナックをやろうと話を進めていたが、ナント契約当日、自信がないと断られてしまった。既に店舗も契約済で支払が発生しており、止めるにもお金が発生していく、という状況。お酒は飲めないけど人と話すことは出来る、それなら自分で、と現在の「Bar Feel」の経営に踏み切ったという。 大好きな音楽を取り込み、自分の好きな店づくりのため開業5年後には6階から広さが約2倍の現在の7階へ移転し、壁面には大迫力でテレビに大好きなバンドを映している。リクエストがあれば、違う音楽も。現在は、そんな音楽好きが集まる店になっているそうだ。 メニューブックは、お店にない。お客様が自分で飲みたいものを飲める“しかけ”作りが大事だと話す。お客様が飲みたいものを自由に自分で選べる、そんな風に気軽に過ごしてほしいと語る。 お店をオープンしたい人は、お客様の中にも居てアドバイスを求められることも多いそうだ。「やってる人とやっていない人の違い、それは選択肢しかない、勇気がないとか色々なことを考えてやらない人が多い、やると決めたら、良くても悪くてもどちらにしても結果は出る。ダメなら違うことをやれば良いと、自分は決めて良かった」と話す。色々な出会いがあり、その人の気持ちや想い、考え方に触れることが出来る。それが店をやった結果。完璧なものほど脆く、不確かなものほど希望に溢れている、と語る。

大事だけれどお客様の意見に惑わされず、ぶれない
三好 真奈美 氏
居酒屋平成15年6月


会社に入社後2年目から夜学で調理師学校に通い、1年半ほどで免許を取得。8年9か月勤めた会社を退職し、準備期間を経て「サンドウィッチとサラダ シュクル」をオープン。会社時代から取引先に厨房機器や備品等、中古品の紹介を頼んでいたため、初期設備費用は抑えられたという。
しかし、スケルトンだった店舗の内装には費用が掛かった。それも今では減価償却を終え、既に回収できていると語る。
それから3年8か月後「おばんざいとお酒 シュクル」に変更した。
当時、桑園駅周辺に大型スーパーが出来、予備校や問屋街がマンションに立ち替わる中、喫茶店での経営には限界を感じたという。
元々食べ歩きが好きで京都のおばんざい屋さんへの憧れから、大皿を並べたカウンターと小上がりのお店に改装し、リニューアルオープン。
飲み放題は宴会以外はなし、一杯一杯大切に飲んでいただきたいからだ。
ある年齢になったらお店を閉めようと思っていたが、会社勤めのご主人に「これだけ長く続けていたら、お店の中でコミュニティが出来上がってる。それを自分の都合で閉めてはいけない」と言われたという。
子供の成長を見せに訪れてくれる方や転勤で戻って来て顔を出してくれた時、続けていて良かったと思うと語る。
勤めていれば休憩などもあるが自分で経営すると、それはあって無いようなもの。飲食店は肉体労働、自分は1日12時間近く立ちっぱなし。お店を始めるなら年齢は早い方が良い。
「食材を選び、調理することは楽しい、お客様と接することも含めて自分はこの仕事が大好き」だと語る。